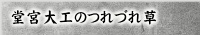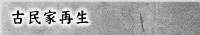●Nさんからのメール
先日、私の元に父上様が静岡市で寺社番匠立川流宮大工であったという御方からメールを頂戴致しました。
立川流といえば関東では有名な宮大工の流派であり、当時は彫刻から全ての諸職工を束ねたすばらしい流派と聞き及んでおります。御方は現在別の職業にてご活躍されているとのことでありますが、お身内の方々は建設に関わるお仕事をされているとのことでした。
流派や現職業が違えど、伝統とその継承されてきた神髄は今もしっかりと受け継がれているようで何かしら親しくお受けしたメールでした。宮大工の流派も沢山あります。私共の先代親方は全国放浪修行の中、伊藤流の業に一つの境涯を得たともいわれております。
継承とは大工の技を学ぶだけではありません。はたまた宮大工だから継承してるとも言い切れません。
伝えられた精神は神仏であり人としての生き方 道徳でもあると思います。
宮大工の現実社会において、やれ俺様は宮大工だ 御堂は何棟建てた、お前達には負けぬ、俺の仕事は日本一だ、私は歴史を知っている学者大工だ・・などと人前に出ては名誉を勝ち取ろうとする方々が沢山いらっしゃいます。
本当の流派継承宮大工の中にはパン屋さんがいるかも知れません。サラリーマンかもしれません。
我が弟子達には本物の宮大工になって欲しいと拙に願ってます。
(かく申す私もちょくちょく腹の虫がどこかへ飛んでゆきますが・・・)
Nさんメール有り難うございました。
~常光庵主~