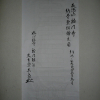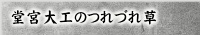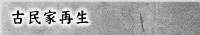秋の色濃くなり、山肌をのぞくと紅葉に染まり落ち葉舞う様子がちらほらと映し出されてきました。
我身心中見直す為と想い、先代墓地掃除にと竹箒片手に上がってみると、一面世界が変わったのかと思えるほどの絨毯でした。 この廟所は、先代がお寺で切られて処分される木々をもったいないからと言いながら一本一本自らの手で樹を植え育ててきたものです。
植樹の時に先代は「今はバラバラで不細工な木々だけどワシが死んだら樹木のトンネルになるぞー。」そんな独り言を云われながらせっせと鍬を持たれていました。
落眼されてから早六年、見事に果実に実がなり、香華にはうっすらとその花を咲かせ皆それぞれに己の本来の姿を自然の中に溶け込ませてきました。
口を開いて人に伝えるときは本気でなくてはならない。その本気は本物の人からのみ出せる。
正しき人であるか。自問自答の日々です。
そうこう反省しながら腰を下ろそうとしたら 「なんじぁや!そのほうきの持ち方は!!」と叱咤されそさくさと下山したのは言うまでもありませんが。
ー 常光庵主 ー
写真・・先代が好んだ寒椿と先代墓前を望む(携帯画像にて失礼)